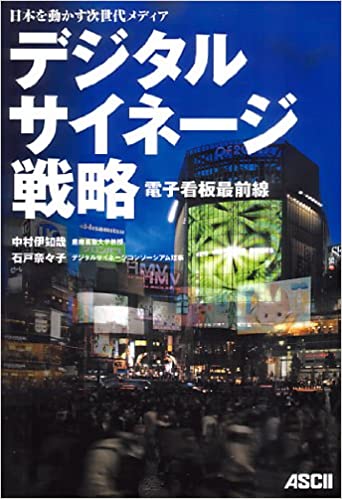デジタルえほん
- 2013.05.23
- テクノロジーは新しい絵の具
デジタルえほんアワードインタビューシリーズVol.4
「テクノロジーは新しい絵の具」
人気の「あかちゃんのあそびえほん」シリーズは累計1100万部のベストセラー。500冊を超える絵本を世に送り出しているきむらゆういちさんにお話をうかがった。
「どの作品も完成度が高いのでびっくりしました。」とデジタルえほんアワードの感想を語る。きむらさんは、絵本作家の卵向けに絵本講座を開催しているが、デジタルえほんに関しては、企画をどう考えればいいのか、これまで今ひとつ分からなかったという。しかし、アワードの作品をみると、デジタルならではのよく考えられた企画が多く、「こうやるのか」と勉強になることもあり、「次は審査員ではなく受賞者側にまわりたい。」と気持ちに火がついたという。
これまでの絵本は、ページを捲るというのが基本だった。しかし、デジタルえほんは、動きが変わったり、音が変わったりするなど、新しいメディアとして成立している。同じ「絵を読む」という名前を掲げているが、メディアとしては違うもの。それを理解していないと、つくる意味がない。
初めて絵本と出会った時にも衝撃を受けたという。本というのは字を読むものだと思っていたが、絵で小さい子に伝えるという表現の仕方があることに驚いたそうだ。そして、次に出会ったデジタルえほん。このメディアの一番の新しさは「参加性」だという。「これまでは送り手と受け手という関係でしたが、受け手がストーリーを変えることもできます。」
きむらさんは、絵本作家であると同時に、23年のキャリアを持つ造形教室の先生でもある。造形は、身近な素材を使って、新しい自分の発想を活かすもの。参加性があるということは、造形教室の世界もデジタルで展開できるということ。市販のおもちゃと手作りおもちゃとでは、おもちゃメーカーがプログラムした通りに遊ぶか、遊び方を自分でつくるかという大きな違いがある。「市販のおもちゃは、説明書通りに遊ばなくてはならず、一歩間違うと遊ばされてしまいます。手作りおもちゃは、一本の棒切れが刀にもなり、ロケットにもなる。自由に発想ができるのです。」作り方は教えたとしても、目的は自分で設定しなくてはいけない。デジタルも同じ。これからのコンテンツは、遊ばされるのではなく、遊べるものがどれだけ生まれてくるかということの勝負だと語る。具象形態のおもちゃではなく、抽象形態のおもちゃ。デジタルえほんは、まだ参加性はあっても、自由に作るというところまで至っていないものが多い。「まだレゴを提供するまでには至っていない。」
また、造形教室を開催していると、時間内に完成しない子がいる。続きは家でやってね!と伝えても、家はマンションで汚せないからこの教室にきているのだ、という答えが返ってくることがあるという。色々な環境で生活している子どもがいる。「材料をふんだんに使える子どもも入れば、家で素材を広げて創作することが叶わない子どももいます。しかし、この画面ではどんな子も平等に使えます。」準備がいらない、空間がいらない。条件がそろわなくてもクリエイティブ活動に参加できる。
もう1つ、きむらさんがデジタルえほんに期待している要素があるという。それは「楽しく教える」ということだ。子どもにとって、もともと遊びと勉強は一緒のものだった。「兄弟でプロレスごっこをしていると遊びに見えるけれど、ライオンはそうやってじゃれあって狩の勉強をしているわけです。」しかしいつの間にか、イヤイヤやるものが勉強となってしまっている。勉強と遊びが分かれてしまった。デジタルの力でそれをもう一度一緒にできないか。
自分でつくること、創作の敷居を下げること、そして遊びながら学ぶこと。そこに新しい可能性を見出しているという。
しかし、デジタルというと子どもへのマイナスの影響を心配する大人たちもいる。「小さい頃、テレビはありませんでした。テレビが登場した時には、その問題点が指摘されました。先日、そんな話を講演でしながら、聞いている大人がもうすでにテレビで育った人たちだったことに気がついたのです。何を問題視しようが、時代の流れに勝てません。そして、気がついたら、みんなそれなりの大人にちゃんとなっています。」漫画ばかり読んでいないで、本を読みなさい!と言われていたけれど、いまでは大人まで電車の中で漫画を読んでいる。さらには、世界で日本の誇る文化は漫画とアニメだと言われ、漫画学科がある大学まで生まれた。「マンガに反対されながらマンガを読んで育った世代が、また違う時代をつくり、デジタルのものを見て育った子どもが大人になってまた次の時代をつくる。その繰り返しです。」
新しいメディアが出て来たからといって、それまでのメディアが消えるわけでもない。「カメラができた時に、この世から絵画は必要なくなると言った人もいれば、テレビができた時に、ラジオがなくなると言った人もいますが、全部なくならないですよね。だから、当然紙の文化もなくなりません。反対するのではなく、正面から取り組んだ方がいいと思います。」どう与えるかが問題で、与えないことは無理なのだ。
しかし、課題もある。ビジネス面だ。これまでも、きむらさんのところには、ネット、ケータイ、ニンテンドーDSなど、電子ものの企画書は数えきれないほど届いていたという。しかし、どれも事業化しそうにない。
「日本国内ではハードの普及率が遅れていることもあり厳しいというのが実際のところです。でもはじめから世界をターゲットにすれば可能性があるのでは?」と指摘する。
紙の絵本はヨーロッパから始まった。日本の絵本の歴史は短い。「子どもの頃は、日本の絵本はありませんでした。よくインタビューで「子どもの頃、好きだった絵本は?」と聞かれるのですが、とても困ります。」しかし、今は日本の絵本は世界のレベルに達しているという。逆に、海外の絵本の翻訳を頼まれると思わず直したくなるものもある。一方で日本の絵本は海外で売れる。きむらさんの絵本も100冊ほど海外で出版されている。先日公開となったきむらさんの絵本が原作となった映画「あらしのよるに」もシンガポールで制作・上映された。マンガ、アニメとビジュアル表現で世界からの評価が高い日本。「デジタルえほんも海外での展開のチャンスがあるのではないか、と思っています。」
これまで、「みなさん色々と試すけれど、なかなかできない」でいたデジタルえほん。デジタルえほんアワードに出会った時に、「ここが次の時代の軌道に乗る企画かな。」という印象を持ったという。作家の立場からすると、希望を感じたという。これまでは出版社が現物のある本をつくり、流通の会社が書店に届けるというシステムがあった。インターネットになり、そのシステムを全部壊す、誰もがそのシステムを持つ可能性を獲得した。資本力といったどうすることもできない世界を作家が変えることができる。その一方で、作家にも変化が求められる。これからの作家はテクノロジーの部分とクリエイティブの部分の両方が必要だと指摘する。理工系と文系の接点。テクノロジーは新しい絵の具だ。絵の具の使い方を分からなければ、頭にある絵を描けないのと同じ。逆に、テクノロジーに優れた人がいても、発想がなければ駄目。その両輪が求められてくる。
きむらさんの絵本は「子どもに伝える」ことではなく、「すべての人に伝える」ことを目標としているという。そんなきむらさんが新しい絵の具でどんな表現を生み出すのか楽しみだ。


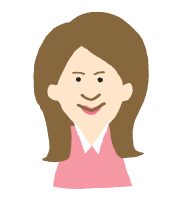








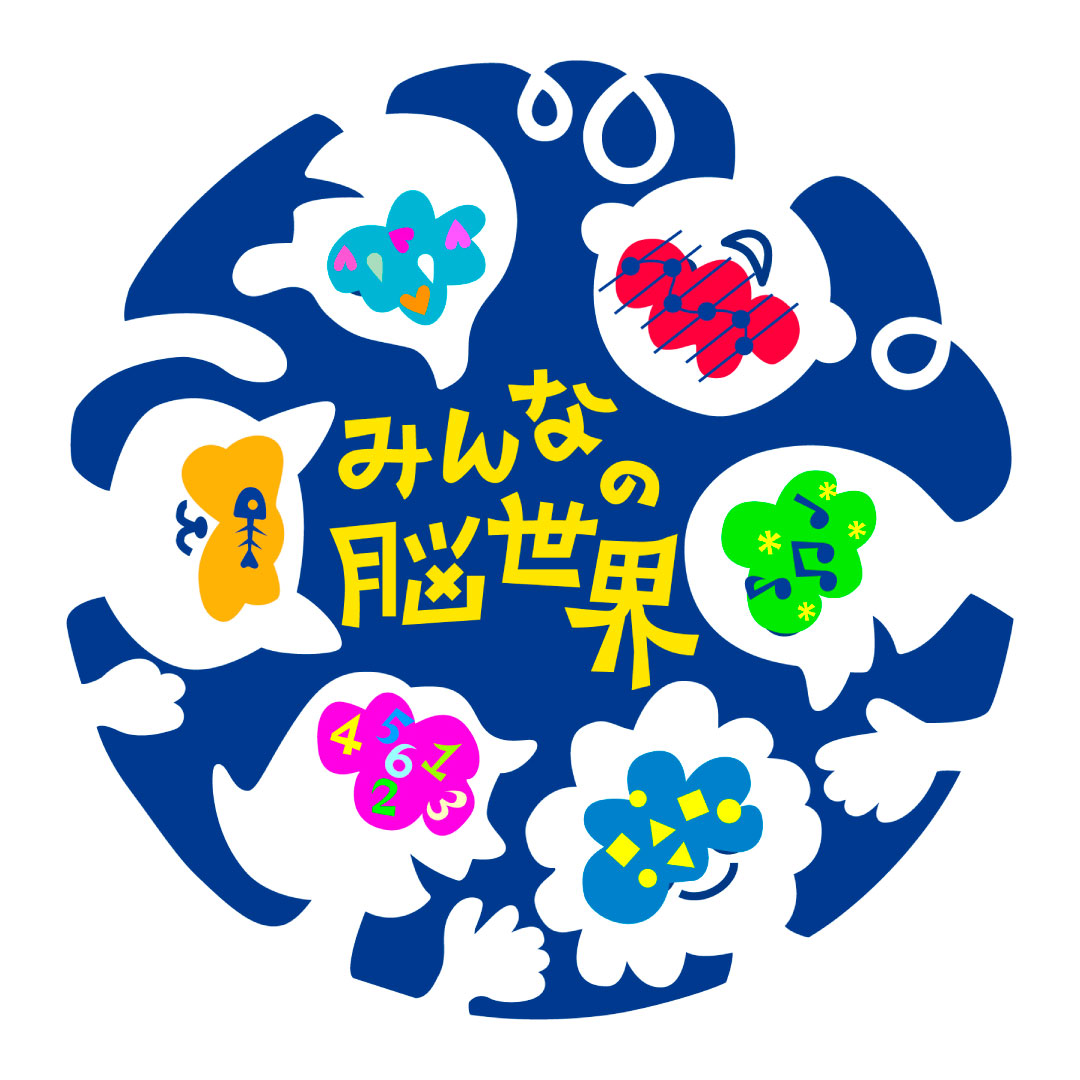



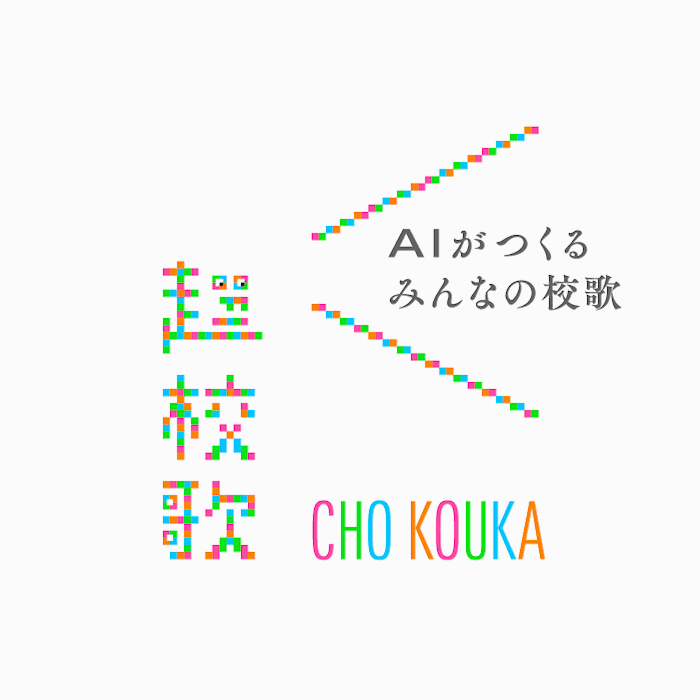














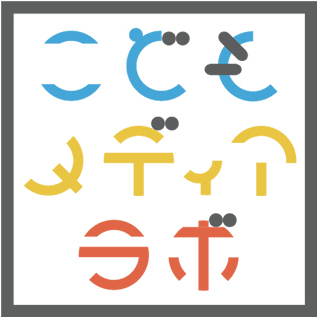

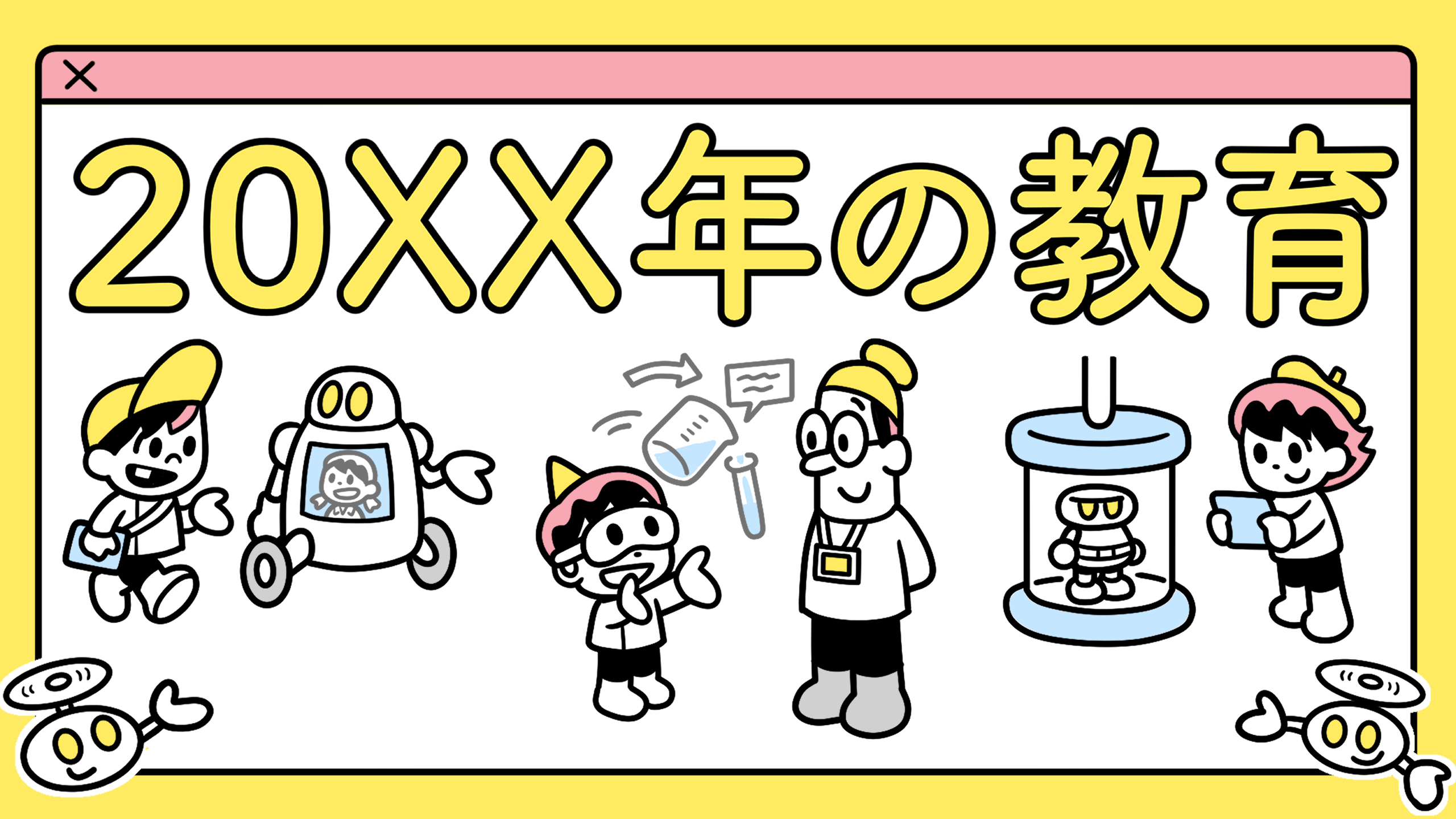






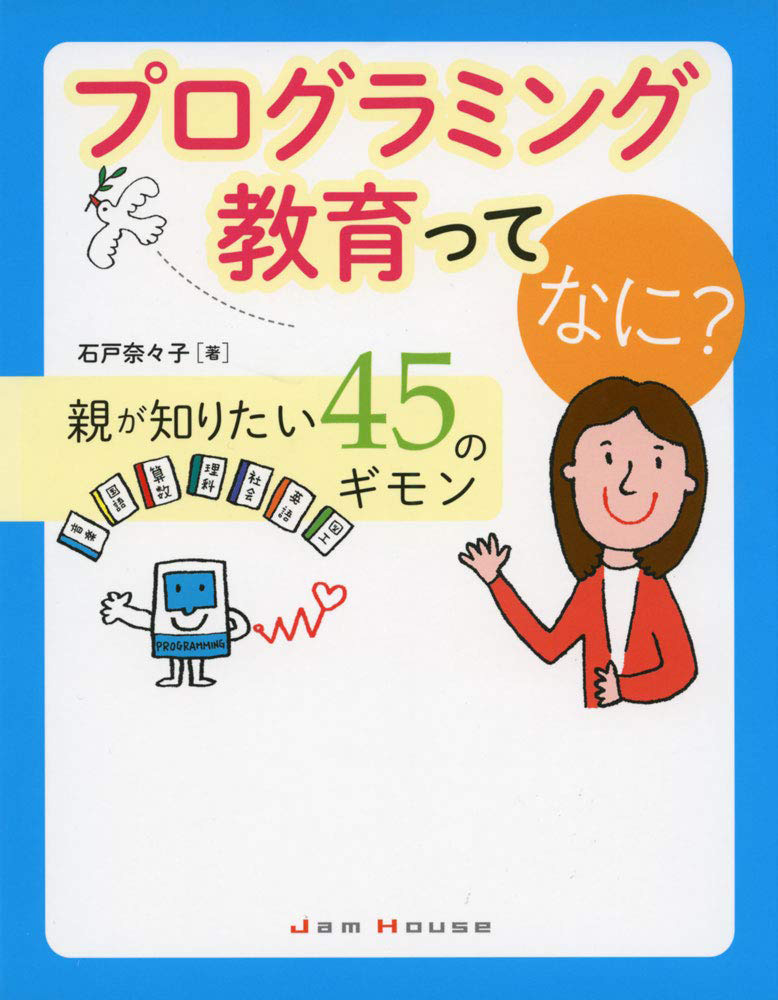


4052047885.jpg )






















1.jpg)