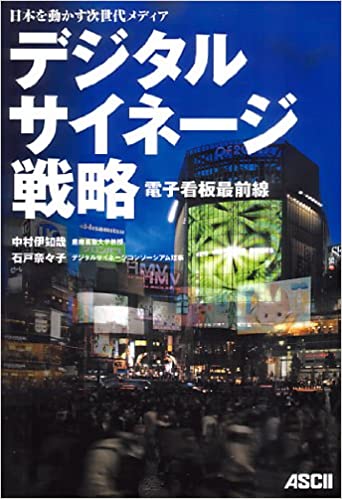デジタルえほん
- 2013.07.25
- 音から子どもの教育に貢献したい
デジタルえほんアワードインタビューシリーズVol.13
「音から子どもの教育に貢献したい」
元気になったり、やさしくなれたり、一歩をふみだす勇気がでたり。えほんがココロにくれるチカラを、ラヂオの音にのせてとどけたい。日本中の子どもたちへ、そして大人たちへ、元気や笑顔をとどけたい。そんな思いから、見ても聴いても楽しめる「ラヂオえほん」を立ち上げた電通の野上章さん、薄景子さん、宮下良介さんにお話をうかがった。
「本プロジェクトを立ち上げるにあたって注目したのは音だった。」お話は耳から入って子どもたちの想像力をかき立てる。「音」から子どもの道徳教育に貢献できないか?というのが「ラヂオえほん」のスタートだった。しかし、「押し付けがましいものにしてしまうとかえって伝わりにくくなる。」そこで、クリエイティブの力で楽しめるものをつくることとなったという。
社内でクリエイティブメンバーを中心に、趣旨に賛同する人を口説いて回った。そうして2011年の夏に誕生したのが「ラヂオえほん」だ。パソコンやスマートフォン、タブレット端末という新しい端末で、親子に「新時代のえほん」をとどける実験的なプロジェクトとしてスタートした。オリシナルアプリをつくると同時に、アプリと連動してラジオ放送で読み聞かせが行なわれている。
独特の雰囲気と温かみのある作品が多いラヂオえほん。このプロジェクトの要のクリエイターとなったのが薄さん。
「これからの子どもたちは、タブレットやスマートフォンをおもちゃとして与えられる。それが最初に手にするおもちゃという可能性もある。だからこそ、絵本をめくるようなアナログ感や、人肌のぬくもりのあるテイストなど、機械ではつくれないものにしたいという思いが強くあった。絵にしても言葉にしても、きちんと人間がつくっているものにするということを意識した。」コンピュータを通じて子どもたちにとどくけれど、伝わる内容は人間的な温かいものにしたいという想いは、作品からもひしひしと伝わってくる。
ラヂオえほんのもう1つのコンセプトに「あの人に送るえほん」がある。それが自分の子どもでもいいし、友だちの子どもでもいい。「一人ひとりのことを思って書くと、複数の人に深く伝わりやすくなる。」何を表現するのかという中身を大事にしているが故のコンセプトだ。
デジタルえほんは新しい表現であり、まだデジタルえほんクリエイターという職が成立しているわけではない。だから、昨年から開催しているデジタルえほんアワードに応募してくる方のバックグラウンドも様々だ。絵本作家だったり、イラストレーターだったり、ゲームクリエイターだったり、主婦だったり。薄さんは、普段はコピーライターとして活動をしている。コピーライターとデジタルえほんの表現。共通項はあるのだろうか? 「ラジオえほんは音にこだわった作品。コピーライターは、ラジオやテレビCMのナレーションを日常的につくっているため、見る文字ではなく、耳から入る物語のつくりかたに慣れている。仕事の延長で絵本風のラジオCMを書く機会もあったので、発想はしやすかった。」
紙の絵本と違い、音声の朗読を入れることによって、表現の違いがあるということだろう。「耳で書く」という表現を薄さんはする。例えば途中で歌に変えていくなど、音として気持ちよく書く、リズムよく書くということを意識した仕事をしているという。その経験が、ラヂオえほんに活かされている。
ラヂオえほんを通じて本当に伝えたいのはお話であり、言葉であるという。紙の絵本でもデジタルの絵本でも、言葉で、音で伝えられないものもある。絵だけで構成されているものや、動きのある絵本などは難しい。音で聴いて世界が広がる絵をデジタルえほんにしていくというのがラヂオえほんの特徴だ。言葉から入るというのはいかにもコピーライター的だ。
ラヂオえほんから生まれた「とんでけおふとん」というお話が、デジタルえほんアワード審査員特別賞を受賞した。
夜ねむるのがこわい女の子。ところがある日、ふしぎな呪文を教わって・・・。おふとんでねむるのがまちどおしくなる、「とんでけおふとん」はそんなお話だ。震災の後、夜ねむるのがこわくなってしまった日本の子どもたちに、毎晩ねむることがちょっとでも楽しみになってもらえたら、という想いでつくられたという。ユニークかつ穏やかな音楽とふわっとやさしい声の朗読に、物語の世界にすっとひきこまれる。テレビを見ているような画面、コミカルな動きとラジオのような優しい朗読、自分でアレンジしながら楽しくつくれるダンスなど、お楽しみポイントがたくさん詰まった作品となっている。
「とんでけおふとん」のお話がまとまった際に、「毒気を入れられるアートディレクターに絵をつけてもらいたいと思った」という。「良い話は、す〜っと流れてしまう可能性もある。そこに毒をいれることで、つかみになる」と語る。宮下さんが抜擢された。
本作品は、えほん動画と、付随する制作アプリで構成されている。後者では、お話に出て来たキャラクターを自分で動かし、音を選び、8コマのアニメーションを簡単につくれるツールが提供されている。宮下さんは、2つの点で苦労をしたという。まず子ども向けにつくるということ。「3歳4歳の子ども向けに広告はうたないので(笑)。小さい子にどう伝えるか、どう楽しんでもらえるか、ということに頭を悩ませた。」もう1点目は、双方向性ということだ。「こちらが提供するものと、触ったユーザーの反応の距離感をどう測っていけばよいか、という計算が難しかったし、勉強になった。」
ラヂオえほんをつくるにあたり、デジタルリテラシーを気にせず、制作スタッフが決められた。宮下さんにとっては、アプリの制作は初めてだ。だからこそ、技術的にできるかできないかと関係なく、表現したいことを言い合い、結果として良い作品に仕上がったという。
えほん動画の方にはインタラクティブは入れていない。一方で、受け手が制作するという究極のインタラクティブともいえる機能を入れた。「インタラクティブ性でスゴイ!と思われたいわけでない。」あくまでも物語の部分で勝負というわけだ。「また過去の制作の経験から、話の途中でインタラクティブを入れるよりも、見せるエンターテイメントに特化してストーリーを伝える部分と、インタラクティブ部分とは分けた方がいいのでは?と思った。」と野上さん。制作アプリの方は、説明、文字を極力入れずに感覚的に分かる映像制作インターフェースになっている。「動画の編集ソフトはたくさんあるが、子ども向けに限定したものは見た事がない。子どもでもすぐできるくらい簡単にしたソフトがあったら面白いな、とは思っていた。」と宮下さん。「幼稚園の先生をしている友人に、これだったら子どもに見せられると言われた時はうれしかった。」という。
最後に、今後の抱負について語ってもらった。
宮下さん「タブレットやスマートフォンは、これからの時代、もう欠かせない。しかしまだ取り組んでいる人は少ないため、全体のクオリティはまだまだ低い。可能性のある魅力的なメディアだからこそ、全体のクオリティが上がっていけばと願っている。」
薄さん「昔は、平屋でドアも開け放して近所のおばちゃんやおばあちゃんがいた。そして、だれかが絵本を読んでくれた。そこでたくさん学んで、大事な気持ちを育ててもらった。しかし、そこにはどうやっても戻れない。いまは、マンションで、隣にだれが住んでいるかも分からない。昼も夜もお弁当を食べる子どもも増えている。そこは変えられない。そしてこういうツールと暮らすのも変えられない。だからこそ、そのような時代の中で、泉のように、あっ、救われた!と思ってもらえるような場として存在したい。せめて、私たちが教わった大事なことを、ときどきふっと見られるようつくり続けて、配信し続けたい。」
野上さん「ラヂオえほんには裏テーマがある。『ココロを救わないといけないのは親』ということだ。子育てのストレスに耐えられなくなり、さまざまな事件がおきている。子どもに見せるということは、親も見るということ。子どもと一緒に見ていると親も癒される。「ああいけないいけない私がこんなに怒っちゃ」そう思ってもらえるようなお話を届けたい。気がつくと幸せな考え方が身に付く、そんな表現を目指している。」
ラヂオえほんは、昨年から複数の賞を受賞し、社内での評価も上がってきているという。また、手探りだったフェーズから、目指すべき方向性が見え始めているともいう。今後はこれをどうビジネスに繋げていくかが課題だ。
ストーリーを書く、絵を描く、音をつくる、そしてコーディングする。デジタルえほん制作にはたくさんの要素がある。電通はすべての人材を持っている会社。今後の展開に期待したい。


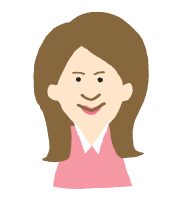








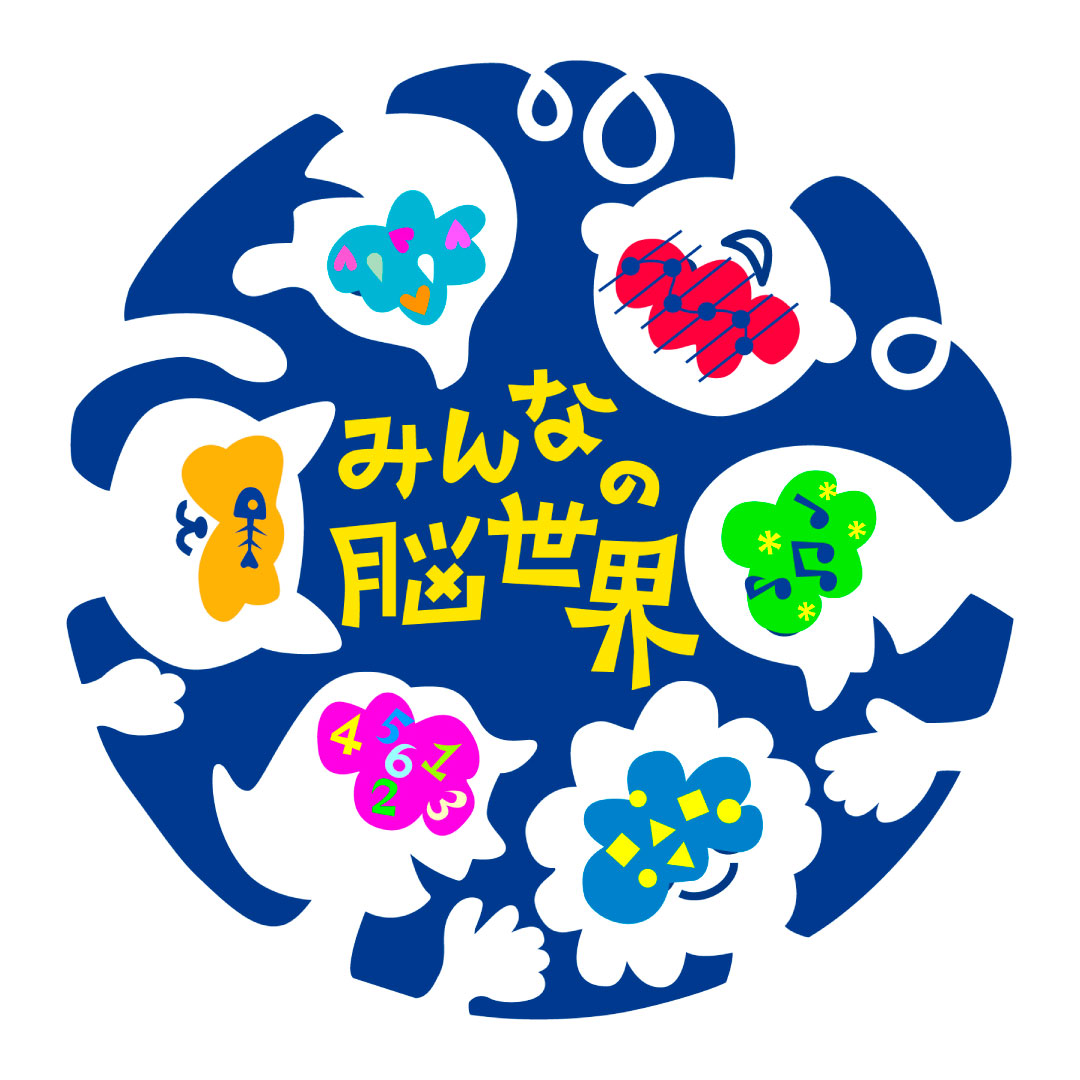



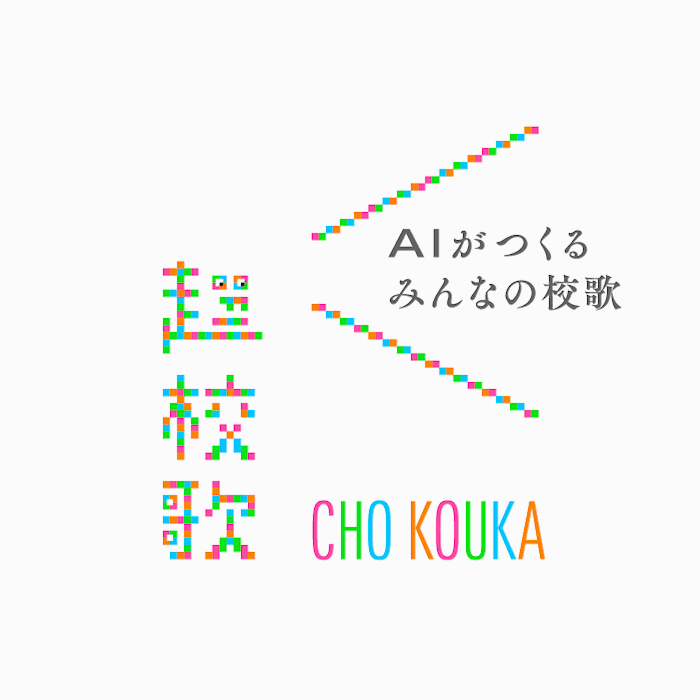














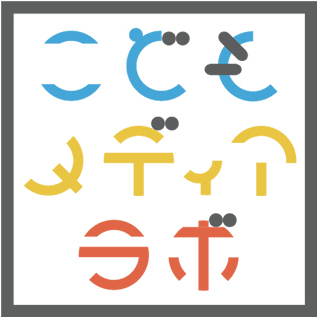

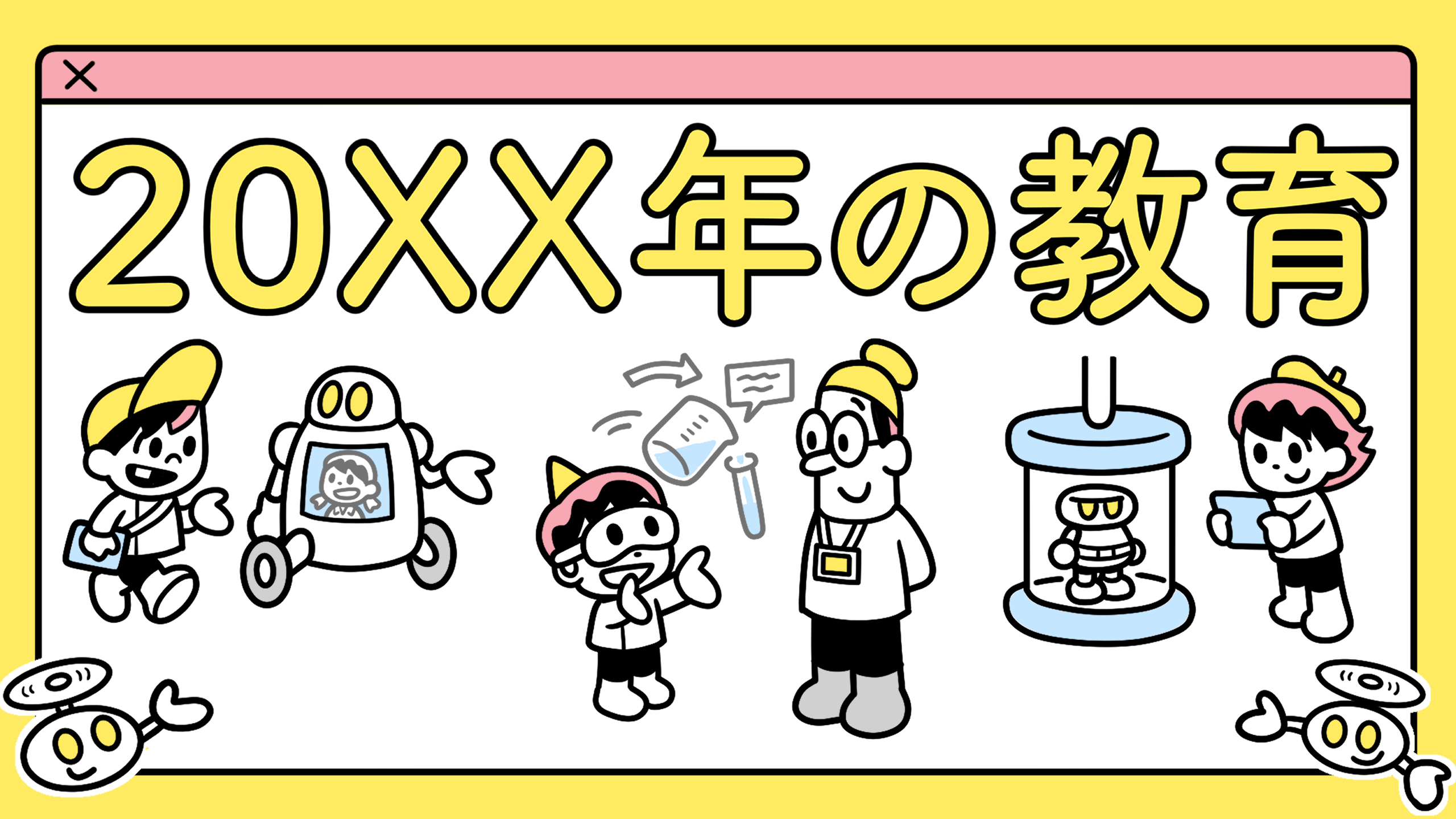






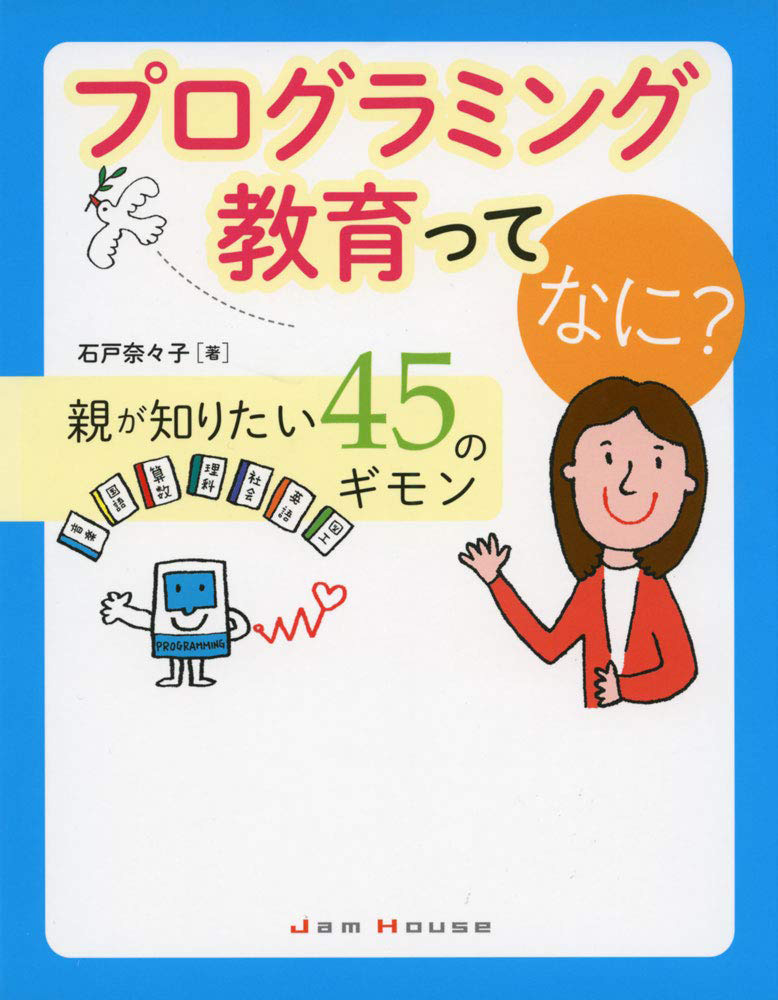


4052047885.jpg )






















1.jpg)